【映画沼 第1回】「映画離れ」なんて悲しいこと言うなよ。
- 大江
- 2017年11月26日
- 読了時間: 4分
この度、合唱団のHPなのに映画について書くという素っ頓狂な任務を仰せつかりました。
インナワTOPの映画とかエンタメ好きの大江です。
突然ですが質問です。
みなさん最近映画館に行ってますか?
そもそも映画自体見てますか?
「映画離れ」なんて時々耳にしますけど、実際のところどうなんでしょうか。
もののデータによれば映画館に行かないだけじゃなく映画そのものを見ないという人は確かに増えているみたいです。(参照:「映画離れ」は「映画そのもの離れ」と「映画館離れ」)
ところがその一方で映画館の入場者数もまた1997年に底をついて以来ゆるやかに増加しているんです。(参照:60年余りの間の映画館数の変化をグラフ化してみる)
映画を見ない人も増えているけど、映画館に行く人も増えている。
それじゃ「映画離れ」なんて必ずしも言えないじゃないですか。
ちょっとこれ印象操作?フェイクなんじゃないの⁉
と私の中のF2層がにわかに色めき立ちましたが、そう単純にはいかないのがこの世の常。
実は入場者数が増えるのと同時に、さらにそれを上回るペースで公開本数も増えてしまっているんです。
そうすると結果としては映画1本あたりの平均入場者数が減っていることになります。
公開本数が多いのは映画ファン的にはうれしいけれども、客が入らなければ産業的にはしんどい。
それこそ去年は「君の名は。」の大噴火があって少し上向いたみたいですが、出版業界の「ハリーポッター」しかり、メガヒット作はこの問題の根本的な解決にはつながりません。
「ボロ勝ちするチームは弱い」ってノムさんも言ってたような気がしますし、この例えはちょっとズレてるような気もします。
余談ですが三十路を越えたおっさんにとって「君の名は。」はドラキュラにとっての日光みたいなものなので、まともに見ると灰になってしまうおそれがあります。
まだ見てない人はお気をつけください。見てしまった人はご愁傷さまでした。
いやー美しさでも人って殺せるんですね。
すいません、脱線しました。
この他に地域や世代の差もありますが、はなはだざっくりまとめてしまうと、上のような世知辛い話はありながら一概に「映画離れ」っていえる状況でもないみたいです。
「映画離れ」って言えないこともなくなくない?くらい。
むしろ「映画離れ」という言葉が一人歩きして映画を見たり映画館に行く人が減ったりしないかがお父さんは心配。子どもはおろか妻もいないけど心配。
これからこのブログで映画を取り上げていくからには、そんな風評被害を未然に防ぐべく「映画離れ」なんて大した事ないんだよって言っといたほうがいいんじゃないかと。
「映画離れ」なんて悲しいこと言うなよ、と。
いやもうこの際、「映画を見るのがナウでヤングのトレンドだ」ぐらいぶち上げちゃってもいいんじゃないかな。
就職面接では「君、映画も見ずにわが社に入ろうだなんておこがましいとは思わんかね」と落とされ、
合コンでは「映画見ない人とか無理なんですけど」と総スカンを受ける。
そんな世界いかがでしょう。
いやだと思った人。安心してください、あなたはまともです。
すいません、錯乱しました。
とはいえ毎日でも映画館に行きたい私としては、毎週いろんな映画が公開されて追いきれないぐらいだし、ミニシアターや名画座も結構な頻度で混雑してるので「映画離れ」の実感はあんまりないのが正直なところ。
時には「客俺だけ」という珍現象が発生して、贅沢気分でスクリーンを独り占めしながらも、ここ大丈夫かしらと心配をかけさせる映画館もあったりしますが…。
109シネマズ木場くん、君のことだゾ。
ネット社会やらグローバル化やらで、多種多様な選択肢が日々増え続けていけば、今まで隆盛を誇っていたものが下降線をたどるのはいかんともしがたい世の流れだと思います。
それでも映画の持つ魅力は変わりませんし、今後も大事な娯楽として存在感を発揮し続けていくでしょう。
えっとなんでこんな話になったんでしょうか。
自由に書いてたらなんかでかい話になってしまいました。
要は
いやぁ、映画ってほんとにいいもんですね by 水野晴朗
ということです。
くっそー。名言を出したら締まるかと思ったらそうでもなかった。
とにかく!このブログではそんな映画の尽きない魅力を微力ながら伝えていくことができたらと思っています。
それでみなさんが映画に思いをはせて実際に見たり映画館に行ったりしてくれたら最高です。
次回からは見た映画の感想とか具体的なことを書いていきます。むしろ今回からそうするべきだったという説もあります。
それではまた次回。
サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ














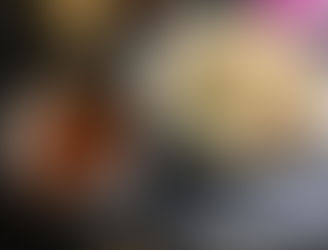
















コメント